専門誌OEの連載第4回が掲載されました
ワークプレイスコンサルティングの現場から
-第4回-
DOUMA代表
小澤清彦
社会的価値観とオフィス環境
我々が「ユニバーサルプラン」(規格サイズの統一)の利点に気づく遥か以前から、スウェーデンでは、すべての従業員に同一サイズのオフィスを提供してきた。スウェーデンの人々がこれを行ったのは、自由に開放できる窓から自然光の射し込む美しくデザインされた家具のあるオフィスでは生産性が数パーセント上昇するという研究結果が動機になっているわけではない。環境のいかなる側面も直截な有効性や効率性によって正当化されなければならないという考えではなく、スウェーデンの人々は美しく快適なオフィスを提供することは、労働者の尊厳を重んじるという社会的価値観に照らして正しいからこそ、平等な環境をすべての従業員に実現させたのだ。
我々は、スペースの有効活用という理由で彼らのユニバーサルプランを採用したが、スウェーデンのオフィスには、それ以外にも様々な効用がある。同一寸法のオフィスはレイアウト変更の際に壁やパネルを移動することなく容易に人々を移動させることができ、経年の改修コストを削減する。小さくても統一されたサイズのオフィスは職場の地位で割り当てスペースを変えるアプローチよりも組織のあらゆる階層に均等にスペースを配分することができる。地位で割り当てる方式だと4割の従業員が6割のスペースを占有するという結果に陥りやすい。さらに、ユニバーサルプランの平等主義的アプローチは、会社が単に地位の高いマネージャーだけでなく、全ての社員を価値ある存在と認めているという環境的メッセージを発信するというボーナスもついてくる。
エコシステムの創造
美しく機能的でコスト効率も良いオフィスを実現する上での課題は、個人からチーム、そして会社全体にわたる様々なレベルで機能するワークプレイスのエコシステムを創造することである。前例のない卓越した商品開発で有名なIDEOのオフィスはまさにその好例だ。(写真1~5)

写真1:IDEO執務エリア/フリップチャートやボードが多用されている

写真2:IDEO執務エリア/プロジェクトごとのプライバシーとオープンな雰囲気が共存している

写真3:自転車のワイヤーラック

写真4:集中個室/内装は吸音パネル

写真5:IDEOリフレッシュエリア/サンフランシスコベイの風景が開放感を生み出す
私が初めてIDEOのオフィスを訪問した時、入口の扉を開けた瞬間から社員同士の会話の声が幾重にも重なってオフィス全体に反響する喧噪に驚かされた。それは、まるで小学校の遊び時間のようだった。創造的思考には遊びが非常に重要なのだ。ひとつの考えかたに捕らわれると、そこから抜け出すのは容易ではない。IDEOのオフィスは非常に異質なため、様々な興味をそそる。それは、IDEOというブランドの市場認知に大いに貢献していると同時に、企業の成功にとって必要不可欠な、才能あふれる優秀な人材を集める点にも寄与している。実務の現場では、そこで働く才能溢れる人々は、オフィス空間に刺激されアイデアの共有や意見交換を自由かつ頻繁に行う。スペースはフレキシブルで、グレードの高い従来型オフィス環境よりもコストはかからない。ブランド価値を高める投資効果を考慮すればお釣りがくるかも知れない。彼らのお気に入りのオフィスツールは、畳一帖くらいの大きさのどこにでも持ち運びできるボードだ。オフィスの一角に大量に準備されており、これを壁に立てかけてアイデアを書き込んだり、ポストイットを貼ったりしてディスカッションした形跡があちこちで見られる。それらはグループ間のアナログな情報共有ツールとしても機能しているように見える。デザイン、企業価値、業務プロセス、マーケティング、学習などが相乗的に進化し、調和的に機能している。IDEOのリーダー達は、部分ではなくエコシステムの全体が如何に機能するかに注目することによりワークプレイスのあらゆる側面を有効活用している。
ワークプレイスソリューションの相乗効果を生み出すために
高いパフォーマンスを示すワークプレイス戦略は、同時に様々なレベルに成功をもたらす。それらは、以下に挙げるように多岐に渡る。こうした効果を発揮するオフィスはどの様にして実現するのだろうか。
・ コスト
・ フレキシビリティー
・ ブランディング
・ 優秀な人材のリクルーティングと定着
・ チームワークとコラボレーション
それぞれの成功が相乗効果を発揮するには、より高い次元の理念が必要になる。スウェーデンのオフィスでは社会的価値観がそれに相当する。企業で言えば組織文化になるだろう。理念をもとに多様な要素を有機的にとりまとめる行為は、組織のエコロジーを適正化することでシナジーを生み出すことである。
組織を活性化する
組織のエコロジーを適正にすることは庭園を計画することに似ている。庭師はうまく行くことを期待して、つつじを日当たりのいい場所に、ひまわりを日陰に、バラを沼地に植えたりはしない。彼らは、与えられた庭の中でそれぞれの品種が生き生きする場所を見つけるのだ。庭師は自然がもたらす広範囲な可能性を追求することで、時間の経過とともにより良い庭へと成長するような、多様で健康的かつ持続可能な植物のコミュニティーを創造する。(図表6)良い庭師は常に実験をくりかえす。彼らは、様々な組み合わせの植物を、種々の場所に植えて結果を観察し、うまく行かなかった場合には、再度植えたり、組み合わせを変えたり、場所を変えたりする。新種を開発するための接木も行う。古いものが新しいものと同居することで、個々の植物ではなく、全体の景観におけるトータルな効果を生み出すのだ。良いオフィスは、良い庭と同様、気配りが必要である。放任状態では種がばらまかれ、育ち過ぎ、やがて枯れる運命だ。

写真6:オフィスをガーデニングの発想で考察する。
生成発展するエコシステムをデザインする。
究極的に我々のつくり上げるオフィスは、関係性や出来事の込み入った網目によって形成されている。そこでは、個人、職種、企業、社会それぞれの価値観によって財務、技術、人間関係といった要素の多様な解釈が展開される。きちんと整理され調和がもたらされれば、組織は、庭と同様に栄光を勝ち得る。組織の価値観やポリシーおよびその実践と相容れないワークプレイス戦略は時間とお金とエネルギーの無駄遣いだ。うまく行く方法は、必ずしも常識にかなうとは限らない。
エコシステムのベンチマーク
ワークプレイスの戦略がうまく行くかどうかは例外なく組織的背景に依存している。従って、マネージャーがワークプレイスの戦略をたてるとき、よく使われるベンチマーキングの手法を用いるのは危険である。先を行く他社の真似をすることは混乱を招くからだ。他社の経験から何も学ぶなと言っているわけではない。むしろ、その戦略が成功した陰には特別なエコシステムが存在していることを理解する必要があるということだ。ワークプレイスの場合には、単にワークステーションのデザインを理解するだけでなく、組織文化、マネージメント、雇用のポリシーとその実践、業務特性や社員の資質なども考慮すべきなのだ。つまり、注目している他社が何をしているかを学ぶ際に、その会社独自のポリシーやその実践の背景にあるものを理解しなくてはならない。例えば、以下の諸点を考慮することが組織についての理解を深める。
・ 組織文化
・ 社員の年齢構成
・ 技術的に洗練されている度合い
・ どのような規制、ルールが存在するか
・ 市場動向
・ 業務オペレーション上の制約条件
これらは、コンサルティングの現場では、インタビューや様々な集計ツールを用いることで、次第に明らかになるが、企業の独自性を見極めるスタンダードな方法論は存在せず、それぞれの組織についてのデータの集積と洞察から導くしかない。
矛盾を許容する
ではなく、「あれもこれも」という考え方および解決策である。このアプローチは、「相互補完的な対極性」とも言うべき中国の陰陽の考え方に通じる。(図表1)
我々は選択の可能性を見渡す時、見かけ上極端に対立するものの間でどちらか一方を選ぶ必要はないのだ。分散化と集中化、画一化と多様な選択、個人とチームなどに関して、両者を受け入れることでパフォーマンスを向上させるべきだ。オフィスレイアウトを例にとれば、企業全体で単一モジュールの家具を集中購買することにより大きなディスカウントを得られると同時に、企業内の全事業部門、さらには各事業部門のチームやグループにおいてそれぞれのワークスタイルやワークプロセスに合わせた家具配置を実現することが可能なのだ。ここで重要な第一の点は、社員が本当に簡便に組み合わせと配置を変えられる家具システムを選ぶことである。また、同様に重要な第二の点は、マネージャーが社員に自分たちの職場環境の改善を奨励することである。それは、会社が社員に対し、信頼と、生産的な職場のための援助を最も直接的かつ目に見えるかたちで示すことのできる手段だ。
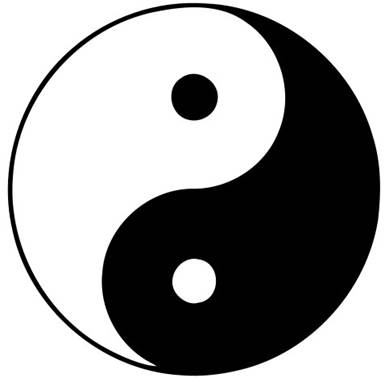
図表1: 相互補完的対極性を示す陰陽図/バランスが重要
我々は、「あれかこれか」という見地で意思決定した方がものごとを複雑にしないと思いがちだ。過剰なノルマと少ないリソースで働かされるビジネスの世界で、日々の仕事をさらに複雑にするような提案が多くの賛同を得られる訳がない。しかし、単純化は時として多様性と選択の幅を伴い、またそれらに支えられるのだという相互補完のバランスを追求する考え方の方がより効果的なオフィス環境を生み出すことに通じる。矛盾を許容することはそれを無視したり抑制したりするよりも労力を必要とせず、さらなるモチベーションにもつながるからだ。健康的なエコシステムは多様性を必要とし、多様性によって繁栄する。ワークプレイスを財務上のポートフォリオと見なしてもらいたい。「全ての卵をひとつの籠に入れてはならない」という投資アドバイスはワークプレイス戦略にとっても有効なのだ。
他にこんな記事が読まれています。
ワークプレイスコンサルティングの現場から
来るべき大変化を前に長期的価値を – 最終回
パフォーマンス向上をもたらすオフィスづくりのために – 第11回
参画意識を高める変革プロセス – 第10回
よりよいチェンジマネジメントのために – 第9回
ワークプレイスの変革をマネージメントする – 第8回
多様な業務環境の一連の繋がりを創造する – 第7回
チームの効率性と個室オフィスの存在意義 – 第6回
知識のネットワークを探求するオフィスデザイン – 第5回
◆高いパフォーマンスを生むワークプレイス戦略 – 第4回
企業ポテンシャルを最大限顕在化させるオフィスとは – 第3回
見えざる資産を見る目の大切さ – 第2回
何故か不人気なワークプレイスコンサルティング – 第1回
小澤清彦(おざわ きよひこ)
ハーバード大学大学院設計学修士、早稲田大学理工学部健陸学科大学院修士、早稲田大学理工学部建築学科卒。
ドウマ㈱代表取締役社長、一級建築士、認定ファシリティマネジャー
100件以上の外資系および日本企業のオフィス企画、インテリア設計に従事した経験と世界的建築家シーザー・ペリやレンゾ・ピアノとのプロジェクト経験を合わせ持つ。
綿密なサーベイに基づくプログラミングとデザインに対する深い洞察を含むワークプレイスコンサルティングにより企業に変革をもたらすオフィスづくりを提案している。
