専門誌OEに連載第11回が掲載されました
ワークプレイスコンサルティングの現場から
-第11回-
DOUMA代表
小澤清彦
少数の有効なルール
オフィスはワークシーンをどのようなものにしたいかという考えを反映する人為的な構築物である。それは、日々の業務で繰り広げられる日常的な慣習を演じる舞台でもある。それらの習慣的行為にはいくつものスタイルがある。例えば、電話をする、コーヒーを飲みながら会話をする、レポートを読む、同僚とプレゼンテーションについて徹底的に議論する、その他数え切れない行為が繰り返される。これらの日常的行為自体は単純なものだ。我々はそれらについて考えたり計画したりするために時間を費やすことはない。しかし、何百、何千とまではいかなくとも何十人かがこうした習慣的行動をとる時、それは密度の濃い相互依存的な行動と人間関係の網の目を形成する。そこには、リズムや分類可能なパターンや内なるロジックが存在し、固有のワークスタイルと社会的モデルを形成する。
オフィスというものは、ワーカーの経験している仕事の内容を反映したものではない。デスクレイアウトやコラボレーションエリアの設え、集中ブースの配置などから仕事の内容を類推することはできないが、ワークスタイルを見いだすことはできる。さらに、組織に内在する社会的モデルを具体的なオフィスの形態から類推することも可能だ。
かつては、役職の上下で構築された組織のヒエラルキーによって支配される社会的モデルがオフィスの形態を決定づけ、その中で繰り返されるワークスタイルも比較的安定していた。しかし、今日の産業構造や市場環境、そしてテクノロジーの激変は、あらゆる業態で組織内の社会的モデルやワークスタイルそのものの変化を生み出し、ワーカーの就労意識の変化とも相まって、オフィス環境の見直しの機運が高まっている。
このような状況に対して無秩序を恐れてはいるが、行動を主体的に起こす強い文化もない場合、矢継ぎ早に方針や規則を押しつけ変化を起こすべきだという衝動にかられ、その一環として表面的にオフィスを変えるというアプローチがとれれる場合も多い。しかし、過剰に細かく規範的なアプローチは息を詰まらせ、結果的に効果が上がらない。代わりに必要とされているのは、ワークプレイスのパフォーマンス向上をもたらすオフィスづくりに役立つ原則である。それらを以下に列記する。
原則1:メタファーを用いてオフィスの再創造を構想する
メタファーは、我々の環境への働きかけ方を形づくる上で重要である。今年発表されたWELL Building Standardという入居者の健康と快適性のみに注目した建築評価基準は、人体の包括的な生理システムと心理的側面の切り口から建物を評価する視点を提示しているが、建物の機能を入居者の心理的肉体的機能と表裏一体のメタファーとして生み出された環境基準と言えるだろう。(図表1)
オフィスやワークプレイスを説明するのに、どのようなメタファーが使えるだろうか。また、そのメタファーによってどのようなアクションが示唆されるのか。もし、ワークプレイスがカフェテリアだとしたら、お客様(社員)が有り難いと感じる品揃えのメニュー(個室オフィス、ワークステーション、休憩エリア)を提供すべきではないか。レストランのメニューと同様にオフィスのメニューもお客様の嗜好が変わるにつれて変化するだろう。また、場所によっても違いが出てくるはずだ。もしオフィスが機械で、その生産活動において効率性、予測可能性、安定性などが求められるとすると、定期的な型どおりのメンテナンスが必要であり、全てのパーツが新品同様に保たれるシステムを考えなくてはならない。さらに、もし我々の働くオフィスが庭園だとしたら、ダイナミックな生態系として全体のシステムやサブシステムがどのように栄養を受け取り、お互いの関係の中で、ある部分の変化が他の部分の変化にどう影響を与えるかを理解すべきだろう。それぞれのメタファーは個々にアクション、ポリシー、ルール、価値観をバランスよく導き、オフィスを再創造することに役立つ。

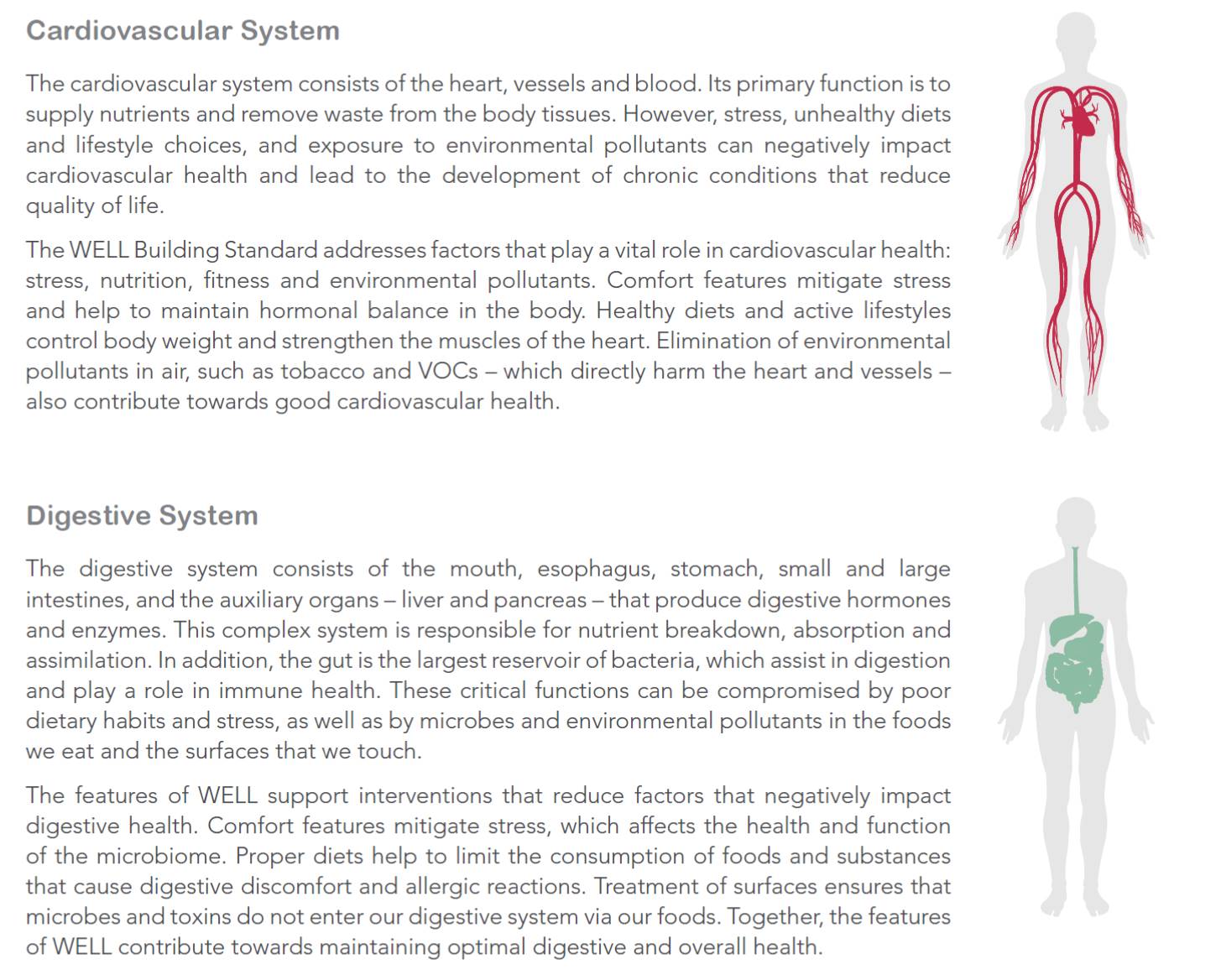
図表1 WELL Building standard 人体の生理機能と建築環境の関係をしめす内容の一部
原則2:多様性と選択の中に秩序を見出すこと
最も骨が折れる根本的な組織のジレンマのひとつは、秩序と無秩序、柔軟性と選択の関係をどのようにマネージメントするかという問題だ。刑務所のような例外を除いては、通常、極端に行き過ぎないことが望まれる。我々には両方が必要なのだ。物事がコントロールされていることは望ましいが、息苦しいのは良くない。我々は、グループの一員であると感じたいが、個人としての特性を犠牲にしたくはない。柔軟性を求めるが、カオスは必要ない。秩序の反対語として無秩序という言葉を使うのは議論を不鮮明にする。もし、無秩序のかわりにバラエティーとか多様性といった言葉を用いれば、両者とも肯定的なものになるだろう。常識的な概念とは裏腹に、秩序と多様性は対立する二つの極として存在するのではない。この2つは互いに補い合っている。
秩序と多様性はお互いを自然に牽制し合い、その結果、どちらも支配的にはならず、両者の存続が可能になる。多様性を開花させるために行き過ぎをコントロール出来るバランスを見出すことが重要である。
原則3:ルールによる管理を排除し、企業文化を築く
組織あるいはワークプレイスに関する全ての非常事態についてルールを設けることは多くの人と時間が必要となり、そのルールが機能することはまれである。デスクの選択から防犯システムに至るオフィスビルデザインの全ての詳細が載っている実施マニュアルは、それ自身の重さで自壊し、マニュアル作成者以外は全員無関心という状況になる。一方、少数の大まかな規則だけを定め、そのルールで規制されたこと以外は全て可能とする方策もある。いつ、どこで、どのように人々が働くかについては、細かく管理すべきではない。ファシリティープランナーやインテリアデザイナーはチームエリアや個人のワークステーションの全ての収納キャビネットや作業テーブルの場所について細かく指定する必要はない。官僚的なルールを立ち上げ、管理し、徹底させるよりも少ないエネルギーと時間とお金で充分である。ただし、選択の幅や多様性を孕んだ運用上の原則や文化的な価値観を少数の項目に絞り込み、それを周知させることに多くの時間と労力を費やす必要がある。多様性と秩序はお互いに助長しあう自然な制約として働く。
原則4:不確実性を有効活用すること
オフィスにおいては「機能的な不便さ」という概念が有効な場合がある。レイアウトや動線計画において明らかに非効率な計画を意図的に行うことで、セレンディピティー の発揮される出会いや偶発的な学習の機会を増やし、業務の生産性を上げるという効果がある。勿論、最短で目的地に着くことだけが重要な時もあるだろう。だが、その他の多くの場合、目的地までの道のりにも価値があるのだ。カーナビが提供する最も早いルート最も景色の良いルートあるいは最も短いルートという選択肢は、どのルートが良いかは全て場合によることを示している。我々は効果、効率、直線的といったものと寄り道をする非効率との間で厳格な選択をする必要はない。それぞれの利点から恩恵を受ければよいのだ。
良いワークプレイスのデザインというものは、単にスペースの物理的な側面だけでなく、それがどう分配され、使われ、管理され、機能するかということについての何千もの意志決定の積み重ねから生みだされ、進化していくものだ。プロフェッショナルであることや手際のよさ、効率的かつ効果的であることとは何を意味するのかについての無数の意志決定は、業務とワーカーのイメージを反映しつつ、累積的にスペースの性格を創造し、やがてその価値を決定する。オフィスというものは常に慢性的な不確実性にさらされており、それに対処するには、硬直したルールよりも多様性や可変性をもつ戦略の方が有効である。継続可能な生態系は融通性が高い。それらは、組織の内外での条件変化に対応することを経て進化しつづけるからだ。
原則5:システムに注目すること
全ての生きたシステムは相互依存によって成り立っているため、ワークプレイスという生きたシステムも、全体の一部を調査し変革するだけでは、組織的なパフォーマンスを向上させることはおろか理解することさえ不可能である。全体のパターンが影響するのであり、個々の要素や側面ではない。その会社が最高のITと人事制度とオフィスデザインと製造プロセスを持っていたとしても、長期的な成功が約束されるわけではない。高いパフォーマンスを発揮するにはワークシステムの全ての要素、即ち、デザイン、空間、IT技術から公式、非公式のマネージメントポリシーと実践、そして企業文化を決定する価値観にいたるまでが、連携している必要がある。
最後に、昨年コンサルティングサービスをさせていただき、先ごろ竣工したPwCコンサルティング合同会社の丸の内オフィスは、基本的にオフィス全体がPwCのロゴが表現する積層するイメージのメタファーとして構築され、さらに多様性や企業文化といった上記の原則も同様に体現したワークプレイスとして実現した成功事例である。(図表2)

受付エリア

ヒストリーウォール

様々な機能が分散されることにより業務のニーズに対応

フレキシブルで機能的なデスク形状

PwCのロゴをモチーフとした重なり合う壁が多様なプライバシーを演出

個人ロッカーもシェアすることを可能にしたシステム
他にこんな記事が読まれています。
ワークプレイスコンサルティングの現場から
参画意識を高める変革プロセス – 最終回
◆ パフォーマンス向上をもたらすオフィスづくりのために – 第11回
参画意識を高める変革プロセス – 第10回
よりよいチェンジマネジメントのために – 第9回
ワークプレイスの変革をマネージメントする – 第8回
多様な業務環境の一連の繋がりを創造する – 第7回
チームの効率性と個室オフィスの存在意義 – 第6回
知識のネットワークを探求するオフィスデザイン – 第5回
高いパフォーマンスを生むワークプレイス戦略 – 第4回
企業ポテンシャルを最大限顕在化させるオフィスとは – 第3回
見えざる資産を見る目の大切さ – 第2回
何故か不人気なワークプレイスコンサルティング – 第1回
小澤清彦(おざわ きよひこ)
ハーバード大学大学院設計学修士、早稲田大学理工学部健陸学科大学院修士、早稲田大学理工学部建築学科卒。
ドウマ㈱代表取締役社長、一級建築士、認定ファシリティマネジャー
100件以上の外資系および日本企業のオフィス企画、インテリア設計に従事した経験と世界的建築家シーザー・ペリやレンゾ・ピアノとのプロジェクト経験を合わせ持つ。
綿密なサーベイに基づくプログラミングとデザインに対する深い洞察を含むワークプレイスコンサルティングにより企業に変革をもたらすオフィスづくりを提案している。
