専門誌OEに雑誌アドバイザーの座談会が掲載されました

写真右上から時計回りに、長坂将光氏、沖塩荘一郎氏、仲隆介氏、小澤清彦氏、OE編集部小関氏、德本幸男氏
‟働き方改革とオフィス環境” を考える
雑誌「OE」アドバイザー4人に、NEOセンター長・仲隆介氏(京都工芸繊維大学大学院教授)をゲストに迎えて10月、ドウマ㈱会議室で座談会を催した。今、世の中は「働き方改革」の大合唱。この働き方改革をキーワードにした「オフィス環境はどうあるべきか」をテーマに、多様な切り口から議論して頂いた。
今回出席の雑誌「O.E.」のアドバイザー諸氏は、沖塩荘一郎氏(日本オフィス学会前会長)、德本幸男氏(㈱竹中工務店国際支店設計部長)、長坂将光氏(グラクソ・スミスクライン㈱ファシリティ・サービスマネジャー)、小澤清彦氏(ドウマ㈱社長)。
IT系を中心とする若い会社は、自由奔放な働き方を展開し、業績を年々アップさせているという仲先生の話があった(下記コラム参照)。こうした事例を念頭に、「働き方改革」「これからの働き方」等について、意見をお聞かせください。
小澤:社歴の永い熟成した大企業のコンサルをする機会もある。そうした会社は自由奔放に働くということとかけ離れた堅い体質をもつ。例えばリフレッシュスペースにいるだけで、サボリというレッテルが貼られる。こうした状況でのオフィス改革はまず、場所や行動に対する古い意味付け、つまりレッテルを外すという、いわばマイナスからのスタートになる。本来なら目指すオフィスはずっとその先にある。仲先生の言われたように働ける企業と、熟成しすぎて硬直した企業の2極化が起こっていると思う。
德本:働き方やオフィス環境を変化させなければいけないという意識や希望は持っているが、それができない企業がほとんどではないか。ある程度の規模になった企業においてどうしたらその変化を実現できるか。分業が進んだ大企業の業務では、管理的な要素の必要性が高くなる。企業の成長に伴って自由奔放な働き方が行き詰まる臨界点がどうしてもある。会社を活性化させるとは何か、なぜそれが必要かという問題意識をもたないと、大きな企業が変化することは難しいと思う。
沖塩:建築家・阿部仁史氏が、建築学会誌2017年10月号で、「オフィス空間の3つの行方」と題して世界の動きをまとめておられ参考になる。①住空間化する労働環境(無料の食べ物、ゲームの提供、睡眠ポッドなど社員により快適で住的な環境を創造しているGoogle)、②テクノロジーの空間化(建築と情報空間を重なり合い、補完し合うよう扱っている3M 本社)、③反転する「仕える空間と仕えられる空間」(オフィスの半分を巨大な廊下としたらここで思いがけない面白いことが起こっているTRI)。
長坂:前職・日本マイクロソフトから英国製薬会社のグラクソ・スミスクラインに転職した。今までの自由でICTの先駆者であるマイクロソフトから製薬会社に移り、本社移転の仕事をせよということになった。会社の性格は真逆だが、移転業務の仕事は同じ。ブランディングは異なっても、ゴールビジョンに沿ったワークプレイスを創造することは同じ。
フェイスブック本社や日本のJINSの場合のように、オーナー企業の場合、ワークプレイス作りはビジョンがカタチになりやすい。オフィス移転というタイミングで入社した私は、現在の会社はレガシーの会社故に、破壊者のような感じの存在だった。破壊と創造を一緒に行う感じで、社内からは あの人は何者? と言われていたが、製薬業は変化しないといけないというマインドは業界内にも、当社の社内にもある。
小澤:当社はグローバル企業の仕事を数多く行っているが、日本のオフィス環境が最も遅れているのではないかと感じる。アジア諸国のオフィスのほうが先進的なオフィスを作っている。なぜ日本ではできないかと疑問がある。足かせや原因を明確にしないといけない。
長坂:今回の仕事をしていてわかったことは、皆さん 伝統文化 という言葉が大好き。変えないことが美徳だと思っている。今回の移転で紙の書類は90%近く削減した。何のために働き方を変えるのかと、それぞれが考えながら日常業務を行うことが重要だと思う。
德本:オフィス創造にビジョンが見えるか、どうかですね。時代の先端をいくオフィスを見るとほとんど創業者のオフィス。トップが2代目、3代目になるとビジョンがどんどん見えにくくなっていく。この段階に至ると、今度はブランディングが重要になる。創業者のビジョンや企業の伝統を常にフレッシュなブランディングに翻訳し、社内外に浸透させられた企業が成功していくのではないかと思う。
小澤:イノベーションには、破壊的と継続的という2つのタイプがある。日本人は破壊的イノベーションを行うことが、苦手な国民性かもしれない。統計があって、日本人は強いリーダーシップが貢献意欲に結び付かないという数字が出ている。ビジョンを掲げ、さあ一緒にやろうといってもついていかない特殊なマインドセットを持っている。一方、日本以外のほとんどの先進国では、強力なリーダーシップが貢献意欲の最も重要なドライバーになっている。従って、日本では破壊的イノベーションのためのデストロイヤーは生まれにくいのではないかと思う。
仲:オフィス改善の提案をする時、担当重役の一声でオフィス改革が中止になったりする。その方々に理解をして貰うのに多くの事例を見せて説明したいが、その機会が作れない。直接の担当者は懸命にやっているのに前に進まない。尻に火がつくまで、そうした会社は変化しないのかなと思う。こうした理解を示さない方々に変革の必要性をどう伝えるかが課題です。
小澤:コンサル会社として期待されていることは、社内だけでは合意形成が困難な問題に対して、中立かつ客観的な立場で課題を指摘し、調整することだと思う。その意味では言うべきことははっきり言わないといけない場合もある。また、経験的に会社のビジョンの浸透や社内コミュニケーションのあり方、問題解決における権限委譲の重要さといった基本的な課題解決の方向性は、ほとんどの会社で理解されている。従って、問題の所在は実践段階で過去からの慣習などをどう打破するかという点に集約される場合が多い。
仲:顧客企業は変化しないといけないことはわかっている。やらないといけないことはわかっているが、目の前の仕事に忙殺されて、やる時間がないと彼等はよく言う。上層部に多くの事例を示し、説得するがそれは一般論、当社は違うという。皆さん忙しすぎる。
長坂:全部を一度に変える必要はないので、変えられる所から変える習慣をつけようと私は部下に言っている。時間がないのではなく、時間を作る努力をする。自分にとって働きやすい環境を自分で作る。そこがベースラインではないか。
マーケットがこれだけグローバルな環境になってくると、日本国内でエコシステムができている会社なら、日本のガラパゴスの環境の中でほぼ完結している。儲かる領域だけ海外に出ていって、そこで儲けるというなら今までの状況で、業績は同じか微増、微減の状況になっていると思う。
しかし、これだけオープンな環境下で、生産性の低い日本の環境でノンコア業務の部分のコストが高くなってくると、世界の中で戦っていく上で相当なハンディキャップになると私は思う。
德本:グローバルな大企業も製造拠点を海外に移したりして、製造コストの競争力を高めて、常にギリギリの戦いをしている。また、アウトソースをして効率化を図り、少人数で業績を上げようとしている。しかし、それを最終製品まで行っていく総コストという、外部化したコストの総和として考えると、どうなのかと思う。切り離すことは別にどこで効率化を図るのでしょう。
小澤:I T、セキュリティ、ワークプレイス、カフェテリア、オフィスサービスなど、広範囲の分野において、全体最適をどうつくるか、どんなオフィスにしていくのか等、長坂さんのように語れて、実行できる人は少ないというのは大きな課題だと思う。イノベーションには、自律性と創造性が重要であり、そのためにはエンゲージメント(貢献意欲)の高さが求められるが、日本企業の場合、この点で他の先進国に比べ遅れをとっている。米ギャラップ社の最近の調査によると日本のエンゲージメントの高い社員の比率は6 %で、調査した139カ国中132位と最下位クラスであり、米国は過去20年間、ずっと30%を維持している。すごい差がある。一方で日本企業の財務的な数字、特許件数を見てもそれほど悪くはないことから、エンゲージメントの低さをそれほど問題視しない向きもあるが、こうした統計結果が示唆する「働くこと」と「幸福になること」の両立が困難な状況が続けば、このしっぺ返しは、近い将来、昨今顕在化しているブラック企業等の事象を超えたスケールで必ずやってくると思う。
プライオリティ(優先順位)として、もはや経済を第一とする時代ではないと思う。心の問題、ハピネス創造が優先されるべきだ。会社は社員を思いやり、社員の人生観にもコミットするくらいの姿勢が求められていると考えている。人生の大半の時間が働くことに費やされるのであれば、死ぬ1 日前、自分の人生はハッピーではなかったということに気付くような働き方ではいけないと思う。
長坂:例えば品種改良をするのに、タネの開発までするのか、あるいは芽が出た時に適切な価格で買うのか、それは企業戦略です。日本の場合、全部自社でやろうとする。今の若い世代の人たちに投資をしようという投資家がようやく出てきた。ハイリスク、ハイリターンの環境を求める人々も出てきた。そうしたことを考えるとようやくグローバルな環境になってきたと感じる。
小澤:成果主義と言われるが、結果だけを総括され、失敗を許容し、そこから学ぶという懐の深いマネジメントを実践できている企業は少ないと思う。工場の生産ラインで不良品を減らすような発想でダメ出しすることが、結果的に社員を委縮させている。イノベーションを起こすためのプロトタイピングという発想と、従来のマネジメントはかなり違う。デザイン思考と言われながら、その本質はデザイン教育を受けていないとなかなか把握できないのが実情で、教育のあり方も問われている。頭のいい人を集めても、結果的にレポートを見栄えよく書ける人、パワーポイントのうまい人、企画を書くのが上手な人の集団ではイノベーションは起こらない。
仲:大企業で低成長だが、何万人という社員を雇用し、粛々と業務を遂行しているところはたくさんある。多くの社員と家族の生活を維持している。微増でも業績を維持し、社員の生活をきちんと維持するのは価値がある。皆、無理してイノベーティブな会社にならなくても社員の給料が払えるなら凄いことだと思う・・・。すべての企業がイノベーティブにならないといけないのだろうか。
長坂:多分いけないと思う。今後、産業界はグローバル化していく。同じサービスを同じカタチで遂行していくと、コスト構造が複雑な日本のほうが不利な状況になる。例としては日本企業はFMの子会社をつくるが、海外企業は専門性のある業者へアウトソースし、契約期間ごとに適切なサービスとコストに見直すので負担は軽いし、フレキシブルな環境を担保している。世界規模で積み上げると、そういったコストを本業へ再投資していくので、ビジネスのパワーが違ってくる。運営コストも開発コストも同様にもの凄い金額の差が出てくる。
ゲスト・仲氏は内外の最新オフィス事例を紹介しながら、働き方のあり方はどうあるべきかを語った。
その要旨は次の通り。
最近、いろいろなオフィスを見学する機会が多い。アカツキというモバイルゲーム事業を手掛ける会社は、若者たちが働きたいように働いている印象だった。コロプラでは、社員が仕事をしているように見えず、遊んでいる感じがした。ボルダリングを用意するなど、オフィスとは思えない自由奔放な空間でオフィスを構成していた。わが国の多くの一流企業は、長い時間をかけて、働き方を熟成してきた。それぞれのビジネスモデルに合わせたプロセスをそつなくこなせるように訓練され、ミスをしないように管理されているのが一流企業の働き方。一方、アカツキやコロプラをはじめとする若い会社の社員たちはやりたいように仕事をしている。
彼らは、ただ自由奔放に働いているわけでなく、結果を出すために必要な仕事を、社会常識に囚われずに、自ら決めた必要なルールのもとに展開している。そして、着々と業績を上げている。こうした若者たちの新しい働き方は、従来の熟成し、さまざまなルールにがんじがらめになった働き方よりも、生産性は高いのではないか。ヤフーでも床に座り込んで仕事をするなど、自分たちがやりたいように仕事をしている。
また、ヤフーのオフィスの至るところで、アドホックな打合せが多数生まれており、状況の変化にリアルタイで対応するためのメンバー間のインタラクションがとても活発に行われている。変化の激しい現代では、組織の作り方、仕事のやり方自体をデザインし直して、迅速なチームワークを実現する必要がある。そういう点では、若者たちのほうが勝っているかもしれない。生産性を上げるために、働きたいように働くということを大事にして、それを可能にする場所を多様に用意している。そんなオフィスで、彼等は自分の能力を発揮しやすい場を選択して働いている。
新しい働き方を考える時に、こうした若者たちのように、これまでの堅い常識に囚われずに、また、過去の成功体験に囚われずに、新しい時代に合わせた働き方を考える必要がありそうだ。
次の話題は働く臨場感。米国シリコンバレーにあるフェイスブック本社は、1フロアオフィスとしては世界一広い。凄いと思うのは働く臨場感。1フロアに2700人の社員が働いている。これは推測だが、これだけたくさんの社員が同じ空間にいると、オフィスのどこかで、1日数回は、成果を上げたチームが「ヤッター!」という歓声をあげていると思う。当然、オフィス全体にその熱気は伝わり、周りに刺激を与えている。次は自分たちだとやる気を起こさせている。
米国シカゴにあるボーイング本社オフィスは、航空機そのものがオフィスにある。どのような仕事をしていても、航空機を見ながら仕事をしているため、自分は航空機を作る仕事をしていると自覚せざるを得ない。BMW本社オフィスでも、オフィスの上を生産ラインが走っている。ここも自分たちは何のために働いているかがわかるオフィス。目的を意識せずに単に作業をしているのと比べると格段に生産性が高いはずだ。
日本のキャンプ用品メーカー・スノーピーク本社は、キャンプ場にある。ガラス張りのオフィスからキャンプ場が見える。自分たちのキャンプ製品を使って楽しんでいる家族の喜びを肌で感じながら日々、働いている。オフィスには、働く人間の気持ちにダイレクトに入り込んでいく、働く人の気持ちを鼓舞するようなメッセージ発信が可能である。オフィスのこの力はとても重要で、今時代が求めている大事な要素ではないかと思う。
座談会続き・・・
「働き方改革」について、どうお考えですか。
長坂:働き方改革は誰のためにするのかを考えると、企業のためなのだろうが、最後は働いている人に返ってくると思う。当社社員は日々、仕事に忙殺されているが、今回の働き方改革や本社移転を契機に立ち止まり、振り返った時、これがベストな働く環境なのか、働き方なのか、ということを考える良い機会になる。本社移転したオフィスを見て、企業トップも移転コストのことだけでなく、オフィス環境の改善や業務の効率化など、多様な面で使用できると考える、とても良い契機になったと思う。変化することで、自分のQOL
が上がるような持続的な改善プロセスが動き出す。多様な対応ができる環境を自分たちで作っていけることが理想形だと思う。
従来のレガシーの会社は思考回路が止まっており、何事も受け身になる。社員皆さんで判断し、考え、コミュニケ―ションして、周囲の人を巻き込み、考えて創っていく。そうした環境を作っていくのが働き方改革のゴールと感じます。
德本:私はワークプレイスのコンサル担当の部署から、今は海外各拠点の設計を統括して、デザインのレベルを上げたり、競争力を高めたりする仕事をしている。コンサルの仕事をしていた頃は、ゴールの明確化をし、現状を把握して変化のシナリオを作っていた。今、アジアや欧州諸国の自社オフィスの現状を調べ把握している段階だが、各地の状況はすべて異なる。働き方も文化も皆違う。その共通ゴールを“見える化”し、どのように変化をすればいいのか、何を変えないといけないか、ということを自分たちで考える習慣を身につけることが重要と思っている。働き方、働く場所は変えないといけないが、結局は明確なゴールに向かって、自分たちで考える習慣をいかに植え付けるか、各地のマネジメントと共に考えている。
沖塩:日本建築家協会で毎年出している年鑑の原稿を依頼されていた。4月に旭川空港で4時間待たされた時、待合室でその原稿がスラスラ書けた。設計の仕事をしていた頃、仕事のアイデアが湧き出る場は電車の中、歩いている時が多かった。机に向かって仕事をするだけでなく、場所が変わることで新しいアイデアが出てくることも多い。新しい発想を練るには場所を変えること。決まった時間、机に向かっている時代ではない。
小澤:一過性に終わらせないために、今の働き方改革が本質的に会社のための人間づくりから、人間のための会社づくりという転換の契機になることを望む。そうでないと結果的に企業の論理になり、どこかに歪みが出てくる。適当につじつまを合わせたら、将来必ず禍根を残す。「問題はそれが生まれた思考のレベルでは解決しない」という言葉があるが、企業の論理を超えなければ、本当の見直しの契機にはならないと思う。ただし、これは企業の論理を否定するものではなく、企業というものが存続するためにも避けて通れないパラダイムシフトだと考えている。
仲:働き方改革が今、ブームになっており、いいことだと思っている。いいことにしたいなと思う。私は建築出身で、沖塩先生に指導されてその道を歩み出した。だからハードな空間、かっこいい建築を作ることにやる気を感じ、喜びを感じていた。しかし、ある時から気持ちが変わり、建築の中で行われている行為の成果を最大化し、中にいる人をハッピーにすることに価値を感じるように意識が変わってきた。
誰も見たことがない、かっこいいオフィス環境を作りたいという気持ちは薄れてきた。建物の中で働く人々が自分の働き方を見直し、自分と会社が幸福な働き方に変化する。そうした状況作りに介在できるか否かに興味が移ってきている。
最近お手伝いした愛媛県西予市役所は、単なるオフィスリニューアルでなく、地方自治体が働き方改革を実践したもの。1年ぐらいかけて討論を重ね、ワークショップを行い、働き方を変える空間とは何か、を追求した。オフィス改革の結果、職員間のコミュニケーションは多様化し、情報は増え、仲間意識が高まっていった。アンケート調査を行った結果、改革後は自分の成長と社会貢献にやりがいを感じる人が増えた。働き方が変化し、生産性が上がることに役立ったと思う。
クリエイティビティや生産性を向上させる働き方は組織によって違う。どこにでも通用する万能の方法があるわけではないので、当事者を本気になるように巻き込み、彼等にとってのハッピーな働き方を一緒に考え、その考え方を空間につなげていくことが大事。とはいうものの現実は大変で、多様な考えが錯綜し、同じ方向に動き出すまでに相当のエネルギーを費やす。しかし、当事者の方々が決まった方向に向かい、一斉に努力し出すシーンに会うといい光景だなぁと思う。

沖塩 荘一郎 氏
1928年生まれ。東京大学工学部建築学科卒。電電公社で通信施設の建築・設計に従事。1980年東京理科大学工学部建築学科教授、1997年宮城大学事業構想学部教授、東京理科大学名誉教授、日本オフィス学会会長など歴任。著書に「高度情報時代のオフィス環境」「変化するオフィス(共著)」など。
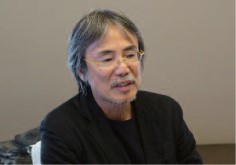
仲 隆介 氏
1957年生まれ。東京理科大学大学院(建築学専攻)修了、東京理科大学助手、M IT客員研究員(フルブライト留学生)、宮城大学助教授を経て、現在京都工芸繊維大学大学院 デザイン経営工学部門教授。情報時代のワークプレイスの設計・コンサルティング・研究活動を行う。著書に「Post Office」(TOTO出版)ほか多数。

德本 幸男 氏
1981年東京大学工学部建築学科卒業。同年、㈱竹中工務店入社。1982〜2002年東京本店設計部。その間1990〜1995年アメリカ竹中設計担当としてニューヨーク、シカゴ等に駐在。2002〜2006年北海道支店設計部長、2006〜2014年ワークプレイスプロデュース本部長。現在、国際支店設計部長。

長坂 将光 氏
1997年、米・ジェームスタウン大学経済学部/芸術学部卒業後、外資系企業でファシリティ、購買、I T、セキュリティ等総務関連業務に従事。2001年 ㈱日本マイクロソフト入社、総務・管理本部プログラムマネージャー。現在グラクソ・スミスクライン㈱ファシリティ・サービスマネージャー。インハウスのFM’erとして効率を重視しつつ快適な職場環境づくりに取り組む。Master of Corporate Estate(MCR)、認定ファシリティマネジャー(CFMJ)

小澤 清彦 氏
ハーバード大学大学院設計学修士、早稲田大学理工学部建築学科大学院修士、早稲田大学理工学部建築学科卒。ドウマ㈱ 代表取締役社長、一級建築士、認定ファシリティマネジャー100件以上の外資系および日本企業のオフィス企画、インテリア設計に従事した経験と世界的建築家シーザー・ペリやレンゾ・ピアノとのプロジェクト経験を持つ。緻密なサーベイに基づくプログラミングとデザインに対する深い洞察を含むワークプレイスコンサルティングにより企業に変革をもたらすオフィスづくりを提唱している。

ドウマ株式会社にて
他にこんな記事が読まれています。
Business Journal にドウマ代表 小澤のインタビューが掲載されました!
OE誌連載記事:ワークプレイスコンサルティングの現場から
来るべき大変化を前に長期的価値を – 最終回
パフォーマンス向上をもたらすオフィスづくりのために – 第11回
参画意識を高める変革プロセス – 第10回
よりよいチェンジマネジメントのために – 第9回
ワークプレイスの変革をマネージメントする – 第8回
多様な業務環境の一連の繋がりを創造する – 第7回
チームの効率性と個室オフィスの存在意義 – 第6回
知識のネットワークを探求するオフィスデザイン – 第5回
高いパフォーマンスを生むワークプレイス戦略 – 第4回
企業ポテンシャルを最大限顕在化させるオフィスとは – 第3回
見えざる資産を見る目の大切さ – 第2回
何故か不人気なワークプレイスコンサルティング – 第1回
小澤清彦(おざわ きよひこ)
ハーバード大学大学院設計学修士、早稲田大学理工学部健陸学科大学院修士、早稲田大学理工学部建築学科卒。
ドウマ㈱代表取締役社長、一級建築士、認定ファシリティマネジャー
100件以上の外資系および日本企業のオフィス企画、インテリア設計に従事した経験と世界的建築家シーザー・ペリやレンゾ・ピアノとのプロジェクト経験を合わせ持つ。
綿密なサーベイに基づくプログラミングとデザインに対する深い洞察を含むワークプレイスコンサルティングにより企業に変革をもたらすオフィスづくりを提案している。
